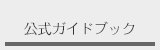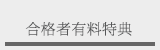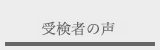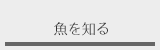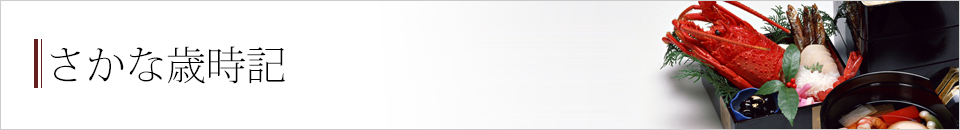
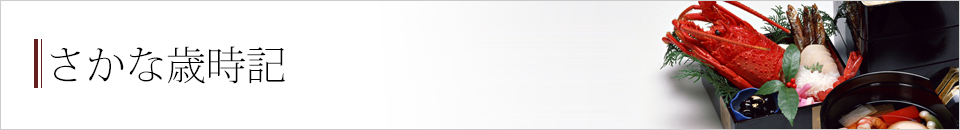
TOP > さかな歳時記 - 二十四節気の魚たち > 大暑
大暑
骨切りあってこそのこの美味
 【解答】④はも
【解答】④はも【解説】関東ではまだまだなじみが薄い鱧(はも)だが、関西では特別の扱いを受ける。関西の夏は鱧料理とともにやってくる。
「祝い事にはタイ、祭にはハモ」といわれ、京都の祇園祭や大阪の天神祭をはじめ夏の関西には欠かせぬ食材だ。なかでも、内陸で新鮮な魚が手に入りにくかった京都ではハモだけは昔から特別扱い。産地である淡路から運んでも生きているほど、生命力に溢れていたからだ。
5月の、走りである水鱧から始まって梅雨の雨水のなかで鱧は成長し、脂がのりはじめる。そして、祇園祭が最高潮に達する7月中旬の山鉾巡行前後から京都の夏の食卓に鱧は日常的に登場し、やがて秋風が吹き、松茸がでると相性のよい「出合いもの」として土瓶蒸しとなる名残の鱧として食べ納めとなる。
 料亭料理として食通にもてはやされつつ、京の家庭料理としてのおばんざいでもある鱧は淡い味わいと深いうまみで京都の人たちを虜(とりこ)にしてきた。
料亭料理として食通にもてはやされつつ、京の家庭料理としてのおばんざいでもある鱧は淡い味わいと深いうまみで京都の人たちを虜(とりこ)にしてきた。ほどよく脂がなじんで、身の締まり具合も絶妙となるこの時季の祭りハモは淡雪のような食感と、淡泊ながら旨みと脂分の後味のある豊かな風味が楽しめるが、ハモをおいしく食べられるのも、骨切りという技あってのこと。
身に左右縦横、呆れるほどの小骨があるハモは、そのままでは食べられたものではない。皮だけ残し一寸(3.03㎝)に24回とも26回ともいわれる神業的包丁をいれてあるおかげなのだ。
骨切りされたハモに葛粉(くずこ)をつけ、熱湯に入れると皮目が縮んで身の襞(ひだ)が白牡丹の花びらのように開くことから名づけられた牡丹鱧。お椀に浮かぶあでやかな白牡丹をおもわせる‘牡丹鱧のお椀'はもはや芸術品。口に入れるや、ただもう幸せだけが拡がっていくのである。
祇園祭の代表料理、鱧寿司。仕出し屋で焼いてもらった鱧は、たれが滴り、照りによって美しい陰影がつけられている。酢飯に実山椒と鱧の照り焼きをのせて巻きかためる、鱧一本丸ごとの寿司だ。
身を上に向けることで、骨切りされた身が立ち、まるで豪奢(ごうしゃ)な山鉾のように動きのある鱧寿司ができる。
手料理は鱧のもうひとつの姿なのだ。
焼きもの、蒸しもの、精巣、卵巣も美味だし、「ハモの笛」と呼ばれる浮き袋や、焼いた皮は和えもので酢の物に。余すところなく利用される、まことに京風の「しまつ」に富んだ魚なのだ。
生命力豊かな魚には、豊かな料理文化があり、鱧づくしといえるほど鱧料理が発達した京都。江戸後期にその京都で出版された『海鰻(はむ)百珍』というハモのレシピ本には、鱧料理だけで実に114通りの料理が紹介されている。
身から腸まで余すことなく使うメニューは、当時からいかに食材が知り尽くされていたかがうかがえる。
そのなかに‘木屋町焼き'なる鱧料理がある。江戸時代から現在に伝わる木屋町焼きは、2枚の身を皮を外側にして抱き合わせにして焼いたひと皿。なぜ、これが木屋町焼きか。木屋町とは、鴨川と高瀬川にはさまれた一角のこと。
川と川、皮と皮、にはさまれているから木屋町焼き。洒落まできかせた鱧料理だ。
広辞苑によるとハモの語源は「ハム」。鋭い歯で何でも「食(は)む」からというのが一説で、同類のウナギのように滋養豊かだ。強い生命力を持つハモの食材としての歴史は古く、縄文時代の貝塚から骨が見つかっている。
暑くなると長い魚がうまくなる。①あなご、②うなぎもその例にもれない。